中古物件に1年住んで分かったこと① ― 住環境 編

中古物件を購入する前に可能な限り情報を集め、内見では構造的な問題がないか自身の目で確認。
これから住む環境についてチェックし、総合的に判断して購入を決意しました。
しかし、すべての問題を事前に調べることは難しく、実際に住んでみなければ分からないことも多々あります。
今回は、1年以上暮らし四季を通じて感じたことや表面化した問題などについてお話します。
新たに見つかったトラブル
雨漏りの根本的な原因
内見時に天井の雨染みが気になっていましたが、不動産屋さんや大工さんの確認により「大きなトラブルではなく大雨や強風による吹き込みなどがなければ問題ない」と回答を得て購入しました。
いざ住んでみると、(毎回ではないが)雨の日には天井やその付近の壁に染みが広がり、天井からは「ポタッ..ポタッ..」と水滴が落ちてくる音が聞こえてきます。

以前大工さんが調査のために開けた天井の覗き口や天袋にある点検口から顔を出し、ライトで照らしながら天井裏を確認してみると上部から雫が落ちてくるのを発見。
それからは、雨が降るたびに天井裏を覗き、雨漏りのチェックを行いました。
その結果、雨漏りが発生する場所は全部で6ヶ所。
雨量や風向きにより発生場所は異なりますが、1ヶ所だけは常に雨漏りを繰り返しています。
原因究明のため水滴の発生源に近づいてみると、屋根材を貫く釘の先端から雫が滴っており、屋根材である板は腐ってはおらず大きな穴も開いていませんでした。
応急処置として、天井裏に空き容器を置き、水滴を受け止めることで雨染みの発生を抑えることにしました。
処置を施してから1年以上経ちますが、新たな雨染みは発生していません。
逆流する汚水

住み始めてから2ヶ月が経ったころ。
これまで問題なく使えていたトイレの調子が急に悪くなりました。
水が流れず便器に汚水が溜まった状態になり、数分ほど放置しないと水位が下がらないという有様。
その時間も日増しに伸び、遂には数10分待たなければ使えないという状態になりました。
それと並行して、トイレ横にある洗面台でもトラブルが発生。
洗顔など水を流そうものなら、どこからか水が漏れたように床が水浸しになりました。
キッチンや風呂は問題なく使用でき、トイレと洗面台のみ排水時に問題が発生しました。
業者に依頼することも考えましたが、料金のことを考え思いとどまり、自力で原因を突き止めようと思案。
トイレ及び洗面台は建物の北側に配置されており、壁を隔て敷地側にマンホールのような設備があったことを思い出しました。
その排水設備らしきところはモルタル製の蓋で塞がれており、どうにかすると開けられそうでした。
(後に『排水桝(ます)』という設備であることが判明)
トイレと洗面台の位置に平行して2つの蓋があり、こじ開けて確認してみると、汚物が溜まり排水が機能していませんでした。
樹木の根がモルタルの亀裂から侵入し排水口を塞いでいることが直接の原因であり、その絡み合った根を取り除くことで問題が解決しました。
それを教訓に、年2回ほど排水桝の点検を行い、清掃することが年中行事になりました。
リフォーム時の施工ミス?

入居当初から洗面台付近からの臭いが気になっていました。
洗面台下部の引き出しを開けると、木材が腐った臭いが濃く漂います。
上記の排水の件が原因なのか、洗面台の接地部分が腐っており、軽く押しただけでへこむような状態でした。
排水できない件を調べるため、洗面台の引き出しや構造的なパーツを取り外して驚きました。
洗面台が接する壁が床から5mmほどのところで途切れており、その隙間が洗面台の幅と同じ長さ(約70cm)で開いていました。
そのため、床下と直結している状態。
洗面台の足元は虫の巣窟になっており、それと排水されない水が原因でその足を腐らせていました。
排水の件よりこちらを優先して対処。
虫を駆除し、ホームセンターで購入したコーキング材で隙間を埋め、応急処置を施しました。
対応を終え冷静に考えてみましたが、どうしてこのような隙間を埋めなかったのか理由がわかりません。
水回りは新たにリフォームされていたため「リフォーム業者が意図的に洗面台で隙間を隠したものなのか」と邪推してしまいます。
静かすぎる環境
"閑静な住宅地" は購入するポイントの一つでしたが、住んでみて驚きました。
あまりにも静かすぎるのです。
区画整理された住宅地であるため、周囲の隣家とはある程度離れた距離で配置されていますが、子供の泣き声やテレビの音などが聞こえてきます。
私自身、そのような音は気にならないのですが、こちらが音を立てると迷惑ではないか気が気ではありません。
移住した目的の一つが "ものづくり" であるため、電動工具などを使用した際に近所迷惑の原因にならないか心配しています。
室内で防音対策を取るか、作業スペースを別の場所に借りるか、今後の課題になります。
四季を通じて
移住先は自然豊かな場所にあるため、四季の景観が楽しめます。
新緑の緑。紅葉を迎えた山。平地を緑で覆う水田そして黄金色の稲穂。
都会では見られない大きな蝶が庭を舞い、様々な野鳥が庭木で翼を休め、その鳴き声で目を覚ます。
ひぐらしの鳴き声で夕刻が告げられ、夜にはカエルや鈴虫の鳴き声が季節を感じさせる。
この自然環境の中、生活していけることが移住して良かった最大のメリットです。
定期的な庭の手入れ

購入した中古物件には広い庭も付いてきました。
売主から数え40年近く手入れされてきた庭には、立派な木々や様々な植物が植えられています。
私が入居するまでしばらく放置されていたため荒れていましたが、時間を見つけコツコツと手入れをしてきました。
その甲斐あって現在は落ち着ける空間になっています。
自宅に庭があるということは、木の枝が隣家の敷地にまで伸びたり、落ち葉で迷惑をかけることもあります。
そのため、手入れも定期的に行わなければなりません。
大きなトラブルに発展させないためにも細目な手入れは重要になります。
夏は虫に悩まされる季節

自然豊かであることはメリットばかりではなく、様々な虫に悩まされることを覚悟しなければなりません。
夏場、庭に出ようものなら大量の蚊に刺され、樹木の選定をしていたときに蜂に刺されたこともありました。
蜂については、毒性の弱い種類であったため大事にならずに済みましたが、数日手や腕の腫れが引きませんでした。
室内にいても蚊の侵入を完全に防ぐことはできず、蚊取り線香は必需品です。
ゴキブリも室内を我が物顔で動き回り、殺虫剤や捕獲しても減ることはありません。
網戸とガラス戸の隙間から侵入していると思われますが、今後は室内に入り込ませないよう対策を取ることが課題です。
余談ですが、夏場にリビング中央をアマガエルがぴょんぴょん跳ね回っていることがありました。
フローリングのダークブラウンとアマガエルの淡い緑色がきれいでしばらく跳ね回っている様子を眺めていました。
これも引き戸の隙間から侵入したものです。
良くも悪くも風通しが良い

購入した中古物件は一人で暮らすには十分な広さがあります。
この広い空間に加え、一階および二階の窓が東西南北に配置されているため、どの方向からも風の流れが感じられます。
そのため、過酷な夏場でも風通しがよく快適に過ごせます。クーラー嫌いの私にとってはありがたい環境です。
一転、冬場になると冷たい外気に悩まされます。
雨漏り確認のため天井材を剥がした部分、先住者が開けた壁の穴、アルミサッシの立て付けが悪いところから隙間風が入り込み、窓を締め切った冬場にも関わらず風の流れを感じます。
応急処置として、段ボール紙や養生テープで穴や隙間を塞いでいますが一時的なものです。
今後修繕を行う際の課題になります。
住んでみて分かった "ご近所付き合い"
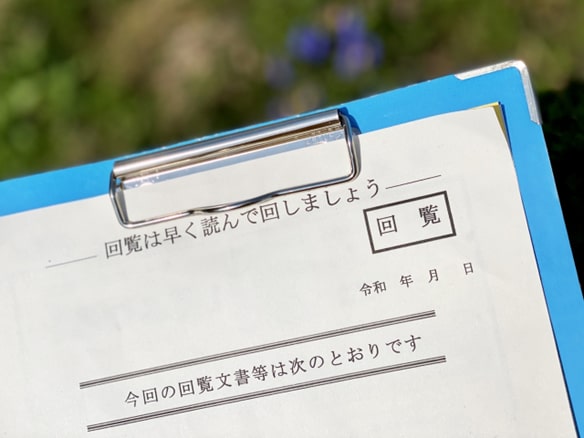
移住先は地域活動が盛んです。
月1~2回は回覧板が回ってきますし、年3回ほどの清掃活動、自治会による祭りやイベントなどが行われます。
土地柄、お年寄りが多いため、これらの地域活動を通じて安否確認や日常の防犯に一役買っています。
新参者の私も自主的に地域活動に参加しています。
(強制的に参加させられるものではないため、気が乗らないイベントについては参加していません。)
清掃活動については、自宅敷地付近の排水溝や近隣の公園をご近所さんと世間話をしながら清掃しています。
また、地域活動は自治会が定めた班ごとに行われ、班長が取り仕切っています。
班長は毎年持ち回りで任されており、今後、新参者の私も例外ではなく任されるでしょう。
ただ、私は単身者であるため、平日など時間的に難しい場合は班の皆さんに助けてもらうことになると思います。
東京で暮らしていたころ、隣近所の住人に対して軽く挨拶は交わすものの、親しく話すことはありませんでした。
しかし、この地に住んでからは挨拶はもちろん、ご近所の奥様方の輪に加わって会話するなど数年前の自分では考えられないことです。
最後に
念入りに調べてもやはり住んでみないと分からないことはあります。
特に中古物件の場合、予期せぬトラブルに見舞われることは多いでしょう。
幸いなことに、私の場合は自らの手で対応できる程度のトラブルで済みました。
物件購入前の下調べ。内見時に構造的な問題の有無を知ることができたこと。
それらが "軽傷" で済んだ要因だと考えています。
また、ご近所付き合いについては良好です。
購入以前に不動産屋さんを通じて近隣の様子を伺っていましたが、実際に暮らしてみるまでは不安でした。
後に井戸端会議で聞いたことですが、私が住んでいる住宅地でも場所によっては隣人トラブルで揉めているところもあるそうです。
新参者でも肩身の狭い思いをせず暮らしていけることは運が良かったとしか言いようがありません。


